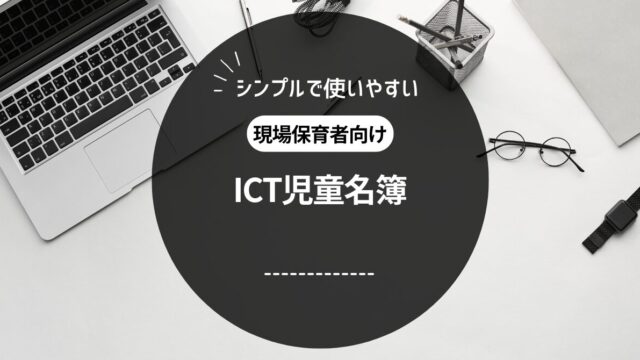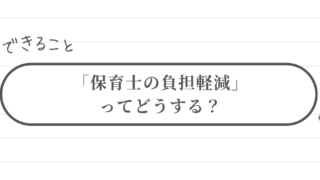目次
はじめに
保育の現場にも、少しずつ「AI(人工知能)」の存在が広がり始めています。
「保育×AI」なんて言葉を見たり聞いたりした方も多いのではないでしょうか?
子どもたちと日々向き合う保育者にとって、
この新しい技術をどう受け止め、どう活かしていくかは、きっとこれからの大きなテーマになるでしょう。
私は、AIを単なる流行や脅威とは捉えていません。
むしろ、保育士が本当に大切にしたい時間や想いを守るための新しいパートナーになりうる存在だと考えています。
今、保育士たちは想像以上に多くの業務に追われています。
- 連絡帳の記入
- 保護者へのお知らせ作成
- 行事の準備や進行管理
- 職員会議や情報共有
- 日々の記録や報告書作成
- 職員間の連携や調整
こうした「子どもと直接関わる以外の業務」が、
知らず知らずのうちに時間とエネルギーを奪っていきます。
本来であれば、子どもたち一人ひとりともっと向き合いたい。
その気持ちは、どの保育士もきっと持っているはずです。
だからこそ私は思います。
「人間にしかできない仕事に、集中できる環境をつくること。」
そのために、AIの力を上手に使う価値がある、と。
この記事では、
- 保育におけるAI活用の可能性
- 実際に取り組んでみた具体例
- AIとの向き合い方の考え方
を、できるだけわかりやすく、丁寧にまとめていきます。
これからの保育を、より温かく、より豊かなものにするために。
AIと手を取り合う未来を、一緒に考えていきたいと思います。
AIって何ができるの?──保育の仕事を支える可能性
保育にAIを取り入れると言っても、特別なことをするわけではありません。
AIは、保育士たちが日々抱えている細かく膨大な業務を、確実に支えてくれる存在です。
ここでは、私が実際に使ってみて感じた、AIの3つの力について紹介していきます。
情報を整理し、見通しをよくする
保育の現場には、毎日たくさんの情報が溢れています。
子どもたちの体調、活動内容、保護者からの連絡事項・・・。
そのどれもが重要ですが、忙しい中で頭の中に詰め込むのは至難の業です。
AIは、散らばった情報をまとめ、
「今どんな情報があるのか」
「どんな対応が必要そうか」
を整理し、見やすい形でサポートしてくれます。
たとえば、
- アンケートの内容を一覧でまとめる
- 行事の準備状況を整理する
- 保護者からの要望や相談内容を整理する
こうした作業を助けてもらうことで、
自然と次に何をするべきかの見通しが立ちやすくなりました。
文章を整え、伝えたい想いをサポートする
保育士の仕事には、「文章を書く」という場面が数多くあります。
園だより、行事案内、保護者への個別連絡。
どれもが、子どもたちの育ちを保護者と共有する大切な手段です。
でも、
- 忙しさで表現が雑になったり
- 誤字脱字に気づかず焦ったり
- 文章作成に技術が伴わない
- 「これで本当に伝わるだろうか」と不安になったり
そんなこともよくあります。
AIに下書きを手伝ってもらったり、
書いた文章をチェックしてもらうことで、
- 文章の精度を高め
- 誤字脱字を防ぎ
- 「想い」に集中する余裕を作る
そんな使い方ができるようになりました。
あくまで「伝えたいこと」は自分自身の中にあります。
AIはそれを形にする手助けをしてくれる、
そんな存在だと感じています。
計画を立て、タスクを整理してくれる
行事準備や日々の保育活動には、たくさんの段取りやタスク管理が必要不可欠です。
- 誰が何をいつまでにするか
- 必要な道具は揃っているか
- 進行に抜け漏れはないか
こうした段取りを整理するのは、
忙しい現場ではどうしても後回しになりがちです。
さらに、保育士はイベントの企画やタスク管理をするプロフェッショナルかと問われれば
私は「はい、そうです」と答えられません。(笑)
そこでAIにタスク整理を手伝ってもらうと、
- 必要な準備リストを作成
- スケジュールに落とし込み
- 抜け漏れチェックをサポート
といった形で、負担を大きく減らすことができました。
結果として、直前のバタバタが減り、行事そのものにも、子どもたちにも、
より穏やかな気持ちで向き合えるようになったのです。
AIは、保育を冷たくする存在ではありません。
むしろ、
温かさを守るために、私たちを支える存在になり得る。
それが、私が実際に感じたことです。
私が実践した保育×AIの使い方
AIを保育の現場に取り入れるときも、私は、
「自分たちの負担を減らしながら、子どもたちにもっと向き合えるようになること」を目指しました。
使い方は、とてもシンプルなところから始めました。
文章作成のサポートを取り入れてみた
保育士は、想像以上にたくさんの文章を書く仕事をしています。
園だよりや行事案内、保護者へのお知らせ、日々の記録。
それぞれに、丁寧な言葉選びと温かみを込める必要があります。
でも、現場は毎日忙しい。
限られた時間の中で、誤字脱字なく、わかりやすく、しかも心を込めた文章を書くのは、なかなか大変でした。
そこで私は、AIに下書きや文章チェックをお願いすることにしました。
- お知らせ文の叩き台を一緒に考える
- 書いた文章の自然な表現を提案してもらう
- 誤字脱字や言い回しのおかしさを指摘してもらう
こうしてAIを活用することで、
文章を作る作業に追われるのではなく、「伝えたい想い」に集中することができるようになりました。
最終的な仕上げは、もちろん自分の手で。
でも、そこに至るまでの時間とエネルギーを、ぐっと節約できたのは、大きな収穫でした。
タスク整理をAIに手伝ってもらった
行事の準備や日々の活動には、常にたくさんのタスクがついてまわります。
何をいつまでに用意するか、誰がどの担当を持つか、
スケジュール通りに進んでいるか――。
これを人の頭だけで管理するのは、どうしても無理が出てきます。
そこで私は、AIにタスクの洗い出しや整理を手伝ってもらうことにしました。
- 行事で使用する準備物リストをまとめる
- 締切ごとにタスクを整理する
- 抜け漏れがないかチェックする
こうして全体を見える化できたことで、
「何が今必要か」「どこに気をつけるべきか」が明確になり、日々の動きに安心感が生まれるようになりました。
事故の状況から、AIと一緒に課題と対策を考えた
さらに、ある場面でAIの力を強く実感したことがありました。
それは、子どものケガが発生したときのことです。
事故の詳細――
- どこで(具体的な状況)
- どんな活動中に
- どんなふうに
起こったのかをAIに伝えた上で、
「事故の要因には何が考えられるか」
「どんな改善策があるだろうか」
を一緒に整理していったのです。
すると、
- 動線の見直し
- 環境設定の工夫
- 職員間での注意喚起の方法
など、具体的な改善のヒントを得ることができました。
もちろん、最終的な判断は現場にいる人間にしかできません。
でも、冷静に課題を整理して、次の行動につなげる助けをAIがしてくれたことは、確かな実感として残っています。
一人で抱え込まず、「一緒に考える存在がいる」
という感覚があったのは、本当に大きな支えでした。
AIは「道具」ではなく、「相棒」だった
こうして、文章作成、タスク整理、課題分析という形で、私は少しずつAIを取り入れてきました。
最初から完璧に使いこなせたわけではありません。
けれど、少しずつ、少しずつ、
AIがそばにいることで、私たちが本当に注ぎたい場所――
子どもたちとの時間、成長を支える関わりに、エネルギーを向けられるようになっていきました。
AIは、ただの道具ではありませんでした。
何かに迷ったとき、考えを整理したいとき、
そっと横にいて、支えてくれる。
それは、まさに「相棒」と呼べる存在だった。
私は、今、そんな風に思っています。
保育者の成長を奪わない──AIとの正しい向き合い方
AIを使うことに対して、
「自分で考える力が育たなくなるのでは」
という声を耳にすることがあります。
結論から言うと、「使い方によってはそうなる」でしょう。
しかし、私自身が実際にAIを仕事の中に取り入れてみて、はっきり感じたのは、
むしろ、考える力がより求められるということでした。
たとえば、AIが作った下書きや、提案してくれたタスク整理。
一見便利そうに見えるけれど、そのまま鵜呑みにしてはいけない。
一つひとつ、自分の目で確認して、
- 現場の状況に合っているか
- 子どもたちにとって本当にいいか
- チームとして無理のない形か
をきちんと考えなければいけません。
AIは答えを押し付けてはきません。
あくまで「こういう方向もあるよ」とヒントをくれるだけ。
最終的にどうするか、どう選ぶかは、私たち人間に委ねられています。
だからこそ、使えば使うほど、考えることをやめない姿勢が大事になる。
私は、このプロセスを通して、むしろ以前よりも、
- より深く考えるようになり
- より現場を細やかに見つめるようになり
- より柔軟に工夫を重ねるようになった
そう感じています。
忘れてはいけない考え方
そしてもうひとつ、忘れてはいけないのが、使わないことによるリスクです。
もしAIを「怖い」「よくわからない」と遠ざけ続けてしまえば、
- 自分たちの負担は減らず
- 無駄な作業にエネルギーを取られ
- 本当に大事にしたい子どもたちとの時間が削られる
そんな未来も、ありうるのだと思います。
だから私は、AIを恐れるのでも、AIに任せきるのでもなく、
「使いながら育つ」
そんなスタンスで向き合っていきたいと思っています。
使いながら学び、
使いながら考え続け、
使いながら、より良い保育を探していく。
それが、これからの時代に求められる、
新しい保育者の姿だと、私は信じています。
保育×ICTのこれまで、そしてAIへの進化
少し前まで、保育の現場に「ICT」という言葉が入ってくるだけで、
どこか特別なもののように感じていました。
出欠管理アプリ、連絡帳アプリ、情報共有ツール――
少しずつ、でも確実に、保育園やこども園の中にもデジタル化の波が押し寄せてきました。
しかし、最初から歓迎ムードだったわけではありません。
- 手書きじゃないと気持ちが伝わらないんじゃないか
- データだけだと、大切な部分が見えなくなってしまうんじゃないか
- 機械に頼りすぎたら、関係性が薄れてしまうんじゃないか
そんな心配や違和感は、どの現場にもきっとあったと思います。
私自身も、最初はどこかで「これでいいのかな」と思いながら使い始めた記憶があります。
でも、使いながら少しずつ気づきました。
便利さが「楽をすること」ではなく、
本当に大切なところにエネルギーを注ぐための手段になりうることに。
実際、ICTツールが浸透するにつれて、
- 保護者への連絡がスムーズになった
- 共有ミスや確認漏れが減った
- 出欠や体調変化の情報がすぐに全員に届くようになった
そんな、地味だけれど確かな変化が現場に起き始めました。
それは、「効率化」ではなく「余白」を生み出す変化だったと思います。
少しだけでも、
- 子どもの表情を見る時間
- ふとした一言を拾う余裕
- 職員同士で声を掛け合う瞬間
そんな温かい時間が取り戻されるきっかけになったのです。
そして今、その延長線上に、AIという新しい技術が現れています。
これまでのICTが「作業を便利にする道具」だったとしたら、
AIは、「一緒に考え、提案してくれる相棒」になり得る存在です。
より高度な情報整理、
より柔軟なサポート、
そして、ときには私たちに新しい視点をくれる力。
そんな可能性を秘めた技術が、
いま、保育の現場にも静かに入り始めています。
もちろん、慎重さは必要です。
大切なのは、ただ新しいものを取り入れることではなく、
自分たちの大切にしてきたものを、どう守りながら活かしていくかを考えることだと思います。
これまでICTに向き合ってきた経験が、
きっと私たちにとって、AIとの関係を築く上でも力になるはずです。
- 無理に使わない
- 使わないと決めつけない
- 使いながら、学びながら、柔軟に向き合う
そのスタンスを持ちながら、AIとも、いい関係を作っていきたい。
そう思っています。
保育士とAIは「相棒」になる
保育の仕事において、
子どもたちと過ごす時間、
ふとした瞬間に生まれる小さな成長、
言葉にならない気持ちを汲み取ること――
それらは、何よりも大切なものです。
AIがどれだけ発達しても、
子どもたちの心に寄り添う仕事は、人間にしかできない。
この確信は、揺らぐことはありません。
だからこそ、私は思います。
AIは、保育士に取って代わるものではなく、
保育士のそばで支えてくれる「相棒」になっていく。
疲れたときに、少しだけ力を貸してくれる。
迷ったときに、別の視点をくれる。
忙しさに追われる中で、忘れそうになった「本当に大切なこと」に立ち戻る余裕を作ってくれる。
それが、AIの存在意義だと、私は感じています。
AIは完璧ではありません。ときに的外れな提案をすることもあるし、
まだまだ人の目で確かめ、判断しなければならない部分はたくさんあります。
でも、だからこそ。
私たちが「どう使うか」を選べる。
どこまで任せるか。
どこを自分たちが考えるか。
どんなふうに手を取り合うか。
それを選びながら、育てていける存在なのです。
これから、保育の現場にもっとAIが入ってくるでしょう。
でも、忘れたくないのは、
AIに合わせるために保育を変えるのではない、ということ。
保育をより豊かにするために、AIの力を上手に借りる。
その意識さえ持っていれば、私たちはきっと、これまでと同じように、
子どもたち一人ひとりの育ちを、大切に見守り続けることができるはずです。
私はこれからも、AIを、仲間として、
ともに育ちあいながら歩んでいきたいと思っています。
おわりに
保育の現場に、AIという新しい存在が加わろうとしています。
それは決して、私たちが大切にしてきたものを壊すためではなく、
もっと深く、もっと丁寧に、子どもたちと向き合うための力を貸してくれる存在だと、私は信じています。
これまで、保育にICTを取り入れてきたときも、
新しいものに向き合うたびに、私たちは悩み、考え、選び取ってきたはずです。
- 手間を減らすためではなく
- 楽をするためではなく
- 子どもたちにもっと時間を使うために
そのために、知恵を絞り、工夫を重ねてきました。
今、AIという新たな選択肢が目の前にあります。
それをどう使うか。どんなふうに付き合っていくか。
答えは一つではないかもしれません。
でも私は、こう考えています。
使うことで、守れるものがある。
使うことで、育めるものがある。
それなら、怖がるよりも、戸惑うよりも、一歩、前に進んでみたい。
AIと手を取り合いながら、これまで以上に、
子どもたち一人ひとりの育ちに寄り添う保育をつくっていく。
それは、保育者としての挑戦であり、
きっとこれからの時代に必要な、一つの新しい在り方だと思うのです。
この記事が、
そんな未来を少しでも一緒に考えるきっかけになれたなら、
心からうれしく思います。
ここまで読んでくださって、ありがとうございました。


![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/477afbc4.2f11f956.477afbc5.4e01940e/?me_id=1278256&item_id=19660012&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakutenkobo-ebooks%2Fcabinet%2F7683%2F2000009167683.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/477afbc4.2f11f956.477afbc5.4e01940e/?me_id=1278256&item_id=24457367&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakutenkobo-ebooks%2Fcabinet%2F2521%2F2000016992521.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/477afbc4.2f11f956.477afbc5.4e01940e/?me_id=1278256&item_id=19660012&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakutenkobo-ebooks%2Fcabinet%2F7683%2F2000009167683.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/25cdcbfc.fe3d00ac.25cdcbfd.3125f061/?me_id=1213310&item_id=21468873&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3334%2F9784805403334_1_3.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/25cdcbfc.fe3d00ac.25cdcbfd.3125f061/?me_id=1213310&item_id=20998566&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2367%2F9784866802367_1_2.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)